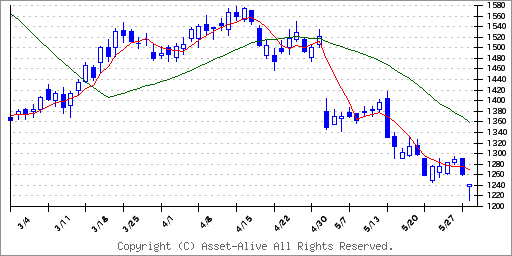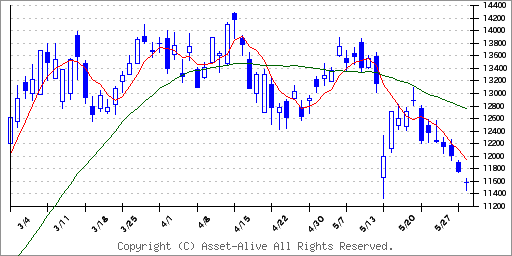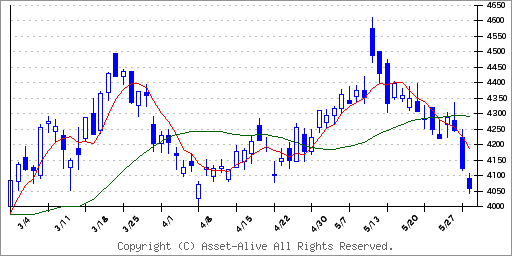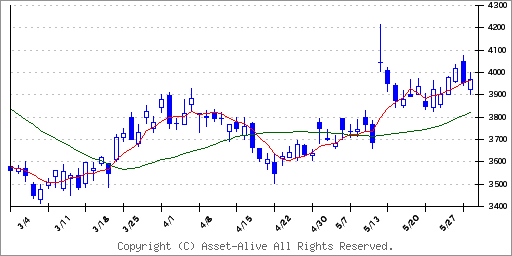株テーマ:培養肉の関連銘柄
培養肉関連株。培養肉は動物の細胞を体外で培養して生産される食肉。植物由来の代替肉と比較して動物性の栄養素を補えるとして新たな代替肉の生産方法として注目されている。
培養肉など、動物の細胞を培養して作る食品について、安全性を確保するため、消費者庁が、ガイドライン案を作る方針を示した。同庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会で決定した。
培養肉関連銘柄
(2269)明治ホールディングス
バイオ技術を活用した食品開発を進めており、培養肉関連の研究にも関心を示している。
(2914)日本たばこ産業(JT)
たばこ事業以外にバイオ事業にも力を入れており、細胞培養技術を活かした食品開発の可能性がある。
(4543)テルモ
医療分野で培った細胞培養技術があり、将来的に培養肉事業への応用も期待される。
(4974)タカラバイオ
細胞培養技術を持ち、再生医療や食品分野での活用が見込まれている。
(1333)マルハニチロ
水産・畜産分野で培養技術の活用を進めており、培養肉市場にも参入の可能性がある。
(2001)日本製粉
食品業界での研究開発力があり、植物性代替肉や培養肉関連の技術開発を進める可能性がある。
カナデビアは、2023年10月にNUProteinと共同で遺伝子組み換えを伴わない培養肉を作り出す「細胞増殖因子」の原料「コムギ胚芽抽出液」の製造工程を自動化する「コムギ胚芽抽出液自動製造装置」を開発したと発表した。培養肉の製造コストは細胞増殖因子が大部分を占めており、細胞増殖因子の原料となるコムギ胚芽抽出液の製造を自動化することで、生産に係る費用を10分の1程度に抑えるという。
荏原製作所は、2023年6月に脱分化脂肪細胞の開発者である日本大学の加野浩一郎教授と、培養肉製造を目的とした共同研究を開始。また、培養肉での活用も期待される細胞培養技術「カルネットシステム」開発のスタートアップ企業であるインテグリカルチャーとシステムのスケールアップで共同開発を開始した。
島津製作所は、2023年3月に伊藤ハム米久、凸版印刷、シグマクシス、及び大阪大学と、「培養肉未来創造コンソーシアム」を設立した。「3Dバイオプリントによる食用培養肉製造技術に関する社会実装の具体的な取り組み」を目的として、世界に先駆けての培養肉食用化の実現を目指す。
日本ハムは、2022年10月に培養肉の細胞を培養する際に必要となる培養液の主成分を、動物由来のものから食品由来にものに置換、ウシやニワトリの細胞を培養することに成功したと発表。培養液のコストで大きな割合を占める動物血清を、安価かつ安定的に調達できる食品に代替できるとしている。
日清食品ホールディングスは、2022年3月に食べられる培養肉の作製に成功。島津製作所と大阪大学大学院工学研究科は、2022年3月に3Dバイオプリントを応用したテーラーメード培養肉の自動生産装置の開発に関する共同研究契約を締結。味の素は、2022年3月にイスラエルの培養肉スタートアップであるスーパーミートに出資。日揮ホールディングスは、2022年1月に培養肉の商業生産を目指し技術開発を行う新会社を設立。オイシックス・ラ・大地は、2021年9月にロブスターやカニなど甲殻類の培養技術を研究するスタートアップである米CD社に出資。